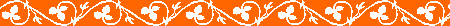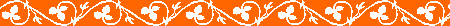
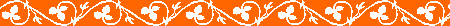
ここでは、ドイツ中世の研究家として第一人者である
阿部謹也先生の著書の中からいくつかを紹介します。
阿部先生の「中世の窓から」は他の本には書かれていない知識が多くて、ドイツ旅行
そんなわけで阿部先生の講演を聞いた後で、私はこの本にサインをしていただきました。
阿部先生は一橋大学の学長を辞められて、現在は共立女子大の学長です。
をしたとき非常に思い当たることが多く、この本の価値を改めて認めたものでした。
以下の本については、阿部先生より引用紹介について快諾を得ています。
ここではまず、 「阿部謹也:西洋中世の男と女 聖性の呪縛の下で、筑摩書房」の中から 一部を紹介します。
アメリカはヨーロッパの中世社会から直接、文化の伝統がつながっている。
絶対王政の経験のない人たちが国を作った。
アメリカではヨーロッパ中世の伝統を受け継いで、
個人が武装することが認められている。ピストルも容易に買える。
陪審裁判という中世の裁判形式が残っている。
(日本にも陪審裁判をという人は、これが中世の名残だとは知っていたろうか?
この阿部謹也先生の指摘はするどい、今まで誰がこんなことを指摘しただろうか)
日本の社会と西欧の社会の大きな違いであるが、
社会関係において何かトラブルにまきこまれたとする。
自分は無実だ、しかし世間を騒がせて申し訳ない、
というのは英語やフランス語やドイツ語に訳せない。
世間を騒がしたのは自分だ。
騒がせたということは、
世間が問題にするようなことをしでかしたということを意味する。
日本語では自分は無実だ、世間が勝手に騒いでいる。
しかし騒いでいる種を自分が提供した形になる
ということは実に不本意だけれども、そのことに関して謝る。
この間には非常に大きな距離があり、その距離を欧米人は理解しない。
もしその本人が、自分は無実だ、
したがって誰が相手だろうと闘い続ける、
といって傲然(ごうぜん)としていたら
日本ではどうなるだろうか。
日本の社会では、たぶん可愛くない奴ということで、
いろんな面で叩かれることになるということが
みんなわかっているので、低姿勢になる。
...ここから次の文章に移るのは理解しにくいかもしれませんね....
「私たちのしたことには、それなりに神聖なものがありました。
私たちはそういう気がしていました。
お互いにそういったではないですか。お忘れになったのでしょうか。」
この言葉が小説の中で発せられるまで、
ヨーロッパ史は千数百年を要した。
(この言葉はアメリカ文学の「緋文字」の主人公ヒロインの言葉である)
阿部謹也:西洋中世の男と女
には男と女の間のことがヨーロッパの歴史で
どう変わっていったかということが書かれてある。
結構難しい内容です。
公開講座をまとめた本だとか。
(高校生の時、ホーソンの緋文字を読んだことがある。
なんとなく(真面目な)真実一路の作家を思わせる小説だった。
路傍の石の作家ですね)
世界中人間社会においては
目に見えない絆によって結ばれた関係がある。
目に見えない絆は、愛とか思想とか信仰とかことばとか音楽とか、
そういうものである。
たとえばことばはその典型であるが、たとえば方言などと
いわれる地域のことばがあるが、
そのことばは、その土地に生まれ育った人間でなければ
100パーセントは使いこなせないものである。
(その地域のニュアンスや特性が反映されているから、
その雰囲気を十分知らないと、その土地のことばは十分使えない)
そして、そのことばを使うと、その土地の風景とか人情とか
その他がパッと浮かび上がってくる。
つまり、その土地のことばとは、感情を充分に包み込んだことばである。
そういうことばを使う人たちの集団があるわけである。
このような目に見えない絆と、ものを媒介とした関係の全体を、
阿部謹也先生は文化だと定義している。
このような、ものを媒介とする関係や、目に見えない絆によって
結ばれた人間の関係は、
人がいるところではどこでも成立するわけだから、
世界中どこにでも文化はある。
そして、その文化のあいだに上下はない。
故郷の山や海に対する思いがこめられた地名なども、
ものの名前にすぎないわけでであるが、
そこには思いがこめられている限り、
その土地の人だけがそのことばを聞いた瞬間に
その光景を頭に浮かび上がらせることができるのである。
その土地の人間にしかわからないという意味で、
非合理なものや不合理なものを含んでいるのである。
だれにでも理解し得るというわけにはいかない、その仲間にしか完全にはわからない
それが文化というもののもつ特性だということである。
その意味では、たとえば料理がひとつの典型である。
日本料理といういい方があるが、それは正確ではなく、
やはり郷土の料理、京都料理とか薩摩料理などというのが本当であろう。
ドイツ料理というものも実はないので、
あるのは地域の料理にすぎない。それを総称していっているだけである。
特定の土地に長く住んでいないとわからないような感覚の世界があって、
それを私たちは文化の世界というふうに一応いっております。
ところが人間関係のあり方はそれだけではなくて、
もうひとつ、文明がある。
文明とは、そういう文化の次元から一歩離陸した(客観的な)人間関係である。
つまり抽象的になるかもしれないが、具体的な地名などには
拘束されない人間関係のあり方があるわけである。
(文化とは特定の集団の共通理解のたまもの。
文明とは民族を越え、地域を越え、時代さえも
超えたものかもしれない)
(文化とは、特別な集団の中にしか存在しないものなら
歌謡曲、コミックなんかも文化かもしれない。
ファッションもそう。ルーズソックス文化、染毛文化、
ヤンキー文化)
>文明とは、そういう文化の次元から一歩離陸した人間関係である。
>つまり抽象的になるかもしれないが、具体的な地名などには
>拘束されない人間関係のあり方があるわけである。
たとえば、性の問題でも、感情をひきずっていないような、
いわば抽象的で合理的で理知的なことばを使った世界がある。
そこでは特定の地域や民族の人だけでなく
一定の能力さえあれば誰もが参加できる人間関係が生まれてくる。
つまり合理的で理知的な人間関係の世界が成立しているのである。
それが文明である。
ヨーロッパは、そういう文明として日本人に意識されたのであった。
イエスは妻が不貞を働いたならば離婚を認めているが、
「神のあわせ給いしもの、人これを分かつべからず」
という言葉のように離婚はできないものと考えていた。
結婚はどこでも子供を生むために行われていたので、
離婚できないとなると、子供を生めない妻と結婚した場合には
家がたえてしまうという重大な問題に当時の人々が直面した。
イエスは、子供のいない夫婦でも離婚することは許されない、
なぜなら子供を生むことが結婚の目的ではないからだ、
結婚とは男女の結合に基づく共同体であって、
死のみがそれを分かつことができる、といった。
この結果、妻の社会的な地位が確保された。
たとえ子供が生まれなくても、妻は安心していることができる。
キリスト教に入信した人の中に、女性が大変多かったことは、
このことも原因のひとつであると想像される。
初期キリスト教徒たちの多くは無産者、つまり貧乏人だったから、
相続すべきものはなかった人が多いからそれほど問題にはならなかった。
しかしイエスの教えが上層社会に広がっていくにつれて、
この問題は後に非常に大きな問題となった。
303年ごろ、スペインの南のエルヴィラという町で宗教会議が開かれ、
司教と司祭・助祭など聖職者のすべては妻をもってはならない、
子供を作ってはならないということを初めて決めた。
しかしそれが実現するためには500年、600年を
経過せざるをえなかった。
このころに中世ヨーロッパの聖職者階層が生まれたといえる。
聖職者階層の成立は、聖なるものの変質の過程である。
古代ローマにおける聖なるものは、聖職者だけが触ることが
できるものに変わっていった。
そこでは聖職者は、生涯妻を持たず独身を通す男性の集団で
なければならないとされた。
初期のキリスト教徒たちの天国を待望した独身運動の
延長線上に特定の集団が生まれ、
いいかえれば、古代末期の殉教を恐れなかった独身主義運動の
エネルギーと成果をいわば継承した集団が
ここに生まれたことになる。
ここでキリスト教が抱えている矛盾が初めから
はっきり示されたことになる。
エジプト、ギリシャ、ローマにおいては
女性は神官・祭司の職に就くことができたのだが、
キリスト教においては女性は祭司職からいっさい排除されたからだ。
こうして独身男性が社会の聖なるものを完全に掌握する体制が
できたときに中世ヨーロッパが始まった。
しかしそれが貫徹するまでは長い道のりだったのだ。
(ここまで読んで、仏教では瀬戸内寂聴さんのように
女性でも僧侶になれることに気がついた。
アメリカでは女性の祭司職や牧師はいないのだろうか、
イギリスではこの頃では女性の登用を認めようとしているようだが)
独身であるべき聖職者の地位が確立してから、
今度はその矛盾を解決するため時間がかかったことが
説明されています(聖職者の恋愛と結婚)。
先にあげた緋文字は聖職者と女性の愛の話だったのです。
この本では昔のエロイーズの話が紹介されたりしています。
読者はイギリス王が外国との領土争いの緊張の中で
跡継ぎを得るため、男の子どもを生まない奥方を離婚する
王様のことを読んで歴史を思い出すでしょう。
あのときから、イギリス国王はカトリック教会と縁を切った
のでした。 イギリス国教会成立。
しかし、この王ヘンリー八世が無理して再婚したアンは女の子しか生まなかった。
次子は男子だったが死産してしまった。
王は怒ってしまった。(なんとしても跡継ぎがほしかった王)
とうとう彼女は離婚に合意しないで殺されてしまった。
(千日のアン)
(ロンドン塔を見学したとき、その話を思い出すと
いっそう興味がわきます。
アンの娘は結局イギリスの女王【エリザベス一世】になるのでしたね。1558)
時間があれば、「中世の窓から」の紹介をしたいと考えています。
この本は疲れたときに読むと私は気分の良くなる本です。
昔も今も人間社会の本質は変わらないことに気がつきます。