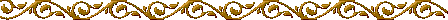作者に電子メールを送れます。
作者に電子メールを送れます。
なかなかむずかしいのです。
するめのように、噛めば噛むほど味の出てくる、そんな感じの本です。
上原専禄先生
対象に惚れ込まなければ、対象は理解できない。 しかし惚れ込んでしまえば、それこそあばたもえくぼで、 見るものも見られなくなる。そのときにどうすべきか。 対象に惚れ込んだ瞬間に身をひるがえして現在の自分に戻って来なければいけない。 こう上原専禄先生にいわれた著者は 「対象に惚れ込んだときに、身をひるがえして戻ってくるということは自分にはできない」 「対象に惚れ込んでしまっているということは、格好のいい状態ではないし、 実体が見えていないかもしれないが、そういう状態になっている自分を どこかでちゃんと見ているもう一人の自分がいる」 と考えた。 わかるということは、それがわかった後で、自分が変わっていなければいけない。 自分が変わっていないわかり方というのは、ただ知識が増えただけだ。 知識なんていうものはほとんど大事なものではない。問題はその知識、あるいは 何かを知ったことによって自分が変わるということだ。変わるということは 生き方が変わるということである。 これも上原先生から言われ著者が考え続けてきたこと。 「どんな問題をやるにせよ、それをやらなければ生きていけないというテーマを探すのですね。」 「あすのことを思いわずらうな。あすのことはあす自身が思いわずらうであろう」 二人の妹の朝食の用意をするお金がないと眠れなかった著者。 イエスの言葉はそのまま受け取れなかった著者の状況。 「生きてゆくということはいかに食べるかだ」というのが当時の著者の心境。 それをやらなければ生きてゆけないテーマはあるはずがない。食物さえあればとにかく生きてはゆける。 しかし、何ひとつ書物をよまず、何も考えずに生きてゆけるか、そんな生活はできない。 一生勉強を続けたいという自分の意志を確認した。 したがって、その後の著者の学究生活は著者自身に満足を与えたことであろう。
修道院の生活
なぜドイツ騎士修道会の研究をするに至ったか。 中学生の時、家の事情で、カトリックの修道院の某施設に入っていた。 敗戦直後、一家は四散していた。 施設の食事は栄養状態が悪く階段を駆け上がることができなかった。 ただ施設に皇族や施設長が訪問する日だけ、見たこともないご馳走が並ぶ。 カナダの司祭に連れて行かれ、別の町の修道院に案内された。 そこで皇族の訪問の日とは比較にならないフルコースのディナーがでた。 最後にはアイスクリームもどっさり出た。 (あるところにはあるのだ) 修道院の豪華な暮らしやヨーロッパの香りにあこがれて司祭になる決心をした著者。 周りも彼の将来に対する期待があった。 母が独立して一軒をかまえたので、1年間の修道院の世話をはなれ、東京に帰ってきた著者。 修道院生活のなかで西欧文化にふれ、キリスト教に接し、そこでの生活と外の生活の違いを感覚で受けとめた。 大学に進んでから卒業論文のテーマに「ドイツ騎士修道会」を選んだ。 気になるドイツ騎士修道会 この組織の全体を明らかにすることを通じて ヨーロッパという世界を明らかにしたと思った。 キリスト教信仰と戦闘とはどう結びつくのか。 修道士が堂々と人殺しをする十字軍とはいったい何か。
ハインペル教授
ゲッチンゲン大学のヘルマン・ハインペル教授 の論文「人間とその現在」 現在の基準を、今日という日におけば昨日はもう過去となる。 基準を今年におけば昨年が過去となる。 現在という基準はきわめて相対的なもの。 歴史の研究は現在からはじまらないといけない。 現在がどこまでさかのぼるかがはっきりしていなければ 過去との関係もはっきりしないから。 現在や現代ということばに絶対的な基準がない。 中世、古代という過去についての時代区分はもっとあやふやである。 日本の歴史家には、歴史というものを自分の外に流れてゆく時間や物事、 そして社会の動きとしてとらえようとする傾向があって、 自分の意識や存在そのものが歴史のなかにあるということを きちんと把握して、分析した人は非常に少ないと思われる。 ハインペルは、自分の意識や外の世界を見たり、分析したりするときの目が、 はたしてすべて現在の目であり、意識であるといえるのだろうかという、 非常に本質的なところから問題を出している。 フィリピンの人びとにとって、アキノ政権が生まれてからが現在であろう。 ソ連においては、かつては1917年の革命が現在のはじまりととらえられていたが、 今ではゴルバチョフ政権のペレストロイカを現在のはじまりとみる人も多いであろう。 現在を規定しているのは過去だけではない。 未来もまた現在を規定している。 将来の計画をたてて現在の生活を営む人、受験勉強のために遊びをひかえ塾通いをする人、 あるいはもっと大きな計画の準備をするために今日の生活をおくる人たちは、未来によって現在を規定している。 ハインペルの自伝的書「小さなバイオリン」 ハインペルの父はシーメンスの技師、大都会ミュンヒェンで暮らしていた。 祖父母はボーデン湖畔のリンダウに住んでいた。 幼いハインペルはリンダウを訪れたとき、リンダウではミュンヒェンとは時間が違うことに気づいた。 時間は数量的にとらえれば万人に公平に流れてゆく。 しかし、時間を人間がどのように意識しているかという点ではそうはならない。 ハインペルは中世のたたずまいの残るリンダウで、リンダウの時間はミュンヒェンとは違うと思ったのではないか。 中世の人びとにとっては現代とは違う時間だったのではないか。 狩人は獲物をつかまえるか、逃げられたときが終わりの時間だった。 5時だからやめよう、などという考え方は歯車時計が普及するまではなかった。 時間が事柄をきめるというのではなく、事柄が時間の枠をきめていたのである。 第1次大戦の敗北を聞いたとき、ハイペルは17歳だった。 彼は祖国の敗戦に衝撃を受けた。そのとき、ミュンヒェンのオペラ座で「魔笛」が上演されていた。 このこともハインペルは大変強い印象を受けた。祖国が破れたのにオペラ座では「魔笛」が上演され、 立派な服を着た紳士淑女が観劇していた。 ハインペルは共通の現在のなかに、さまざまな現在があることを感じとった。 (その人その人で違う現在がある) ハインペルの子どものときの体験が、後の学問に影響を与えたように (学問の意味づけとして)自覚的に生きるために2つの手続きが必要。 1つは自分のなかを深く深く掘ってゆく作業である。 どんな人もものごころついときから、自己形成がはじまっている。 学問の第一歩は、ものごころついたころから現在までの自己形成の歩みを、 たんねんに掘り起こしてゆくことにある。 自分を歴史的に掘り起こす試みでもある。 歴史研究の大事な手続きの第2は 自分の内奥を掘り起こしながら、同時にそれを大いなる時間のなかに位置づけていくことにある。 「もしある作品が完全に現在のなかに埋没し、その時代にしか生まれないものであって 過去からのつながりも、過去との本質的な絆ももたないとしたら、 その作品は未来に生きることはないだろう。 現在にしか属さないすべての事物は現在とともに滅びる」 (ミハイル・バフチーン)
モノを媒介とする関係
ドイツ騎士修道会史の何が明らかになったときに ドイツ騎士修道会が解ったことになるのか。 ドイツ騎士修道会の支配下にあったドイツ中世の農民の顔や 着物、生活内容を知りたい。 古文書を読んでも答は見つからなかった。 解るということは、それによって自分が変わること。 一人の人間がだれかを理解するということは、その人のなかに自分と共通な何か基本的 なものを発見することからはじまる。 古代、中世の人間と人間との関係のあり方は、現代人のそれとは大変異なっているので 現在我々のもっている常識をいったん捨てなければならない。 モノを媒介とする関係 目に見えない絆で結ばれた関係(掟、信仰、習慣) これに気がついたのは、ドイツ人を家に招待したとき、ドイツ人の手みやげの 習慣に気づいてかららしい。ドイツの社会にもとうぜん贈与・互酬関係が見られる。 ただ、少し日本とは違うようだ。お返しを期待して、相手に贈り物をする日本人。 キリスト教の社会では、この世で貧しい人に喜捨するなどの善行を施せば、死後の世界 で天国に行けるというのが常識らしい。神に贈り物をするキリスト教徒というところであろうか。 この場合、貧しい人に贈り物をすることが、神に贈り物をすることの代わりになる。 ルカ伝 「晩餐の席を設けるばあい、友人、兄弟、親族、金持ちの隣人などは呼ばぬがよい。 おそらく彼らもあなたを招きかえし、それであなたは返礼を受けることになるから。 むしろ宴会を催す場合、貧乏人、不具者、足なえ、盲人などを招くがよい。 そうすれば彼らは返礼ができないから、あなたはさいわいになるであろう」 与えられた者には、必ずそれ相応のお返しがあるという報酬関係の原則を前提にして。 お返しをこの世ではなく、天国で受け取るという形に回路を変更したものとみることができる。 ある人が死後に天国で救われたいと考えたとする。 この人がまずしなければならないことは、財産を教会に寄進することである。 教会はその財産の一部を貧民救済にあてるが、大部分は教会の建設その他に使う。 寄進した人にとっては、自分の財産で教会を建てる援助をすることはたいへん名誉なことであり、 それによって天国で救われるということを大勢の人に示すことにもなり、多くの人から尊敬されることにもなる。 天国と地獄という絶対的終着点を基準にして、人と人との間にやりとりされていたモノ (財産)が、教会に大量に入ることになった。 そしてヨーロッパ各地に大聖堂がそびえたつようになった。
機械時計の発明
機械時計の発明は人間社会を変えた。 大聖堂時代に機械時計も発明された。 時計は修道院のなかで祈祷時間を正確にはかるために用いられたが 歯車を用いた機械時計の発明は、その後の人類全体を規定するほどの意味をもっていた。 それまでの時計は、火時計(日時計)や水時計、砂時計などで 自然のリズムに合致したものだった。 中世の人びとにとって、正確な時間を知る必要はなかった。 農民は夜が明けてから陽が沈むまでが仕事の時間だった。 機械時計の発明により、自然のリズムとは違った客観的な時の計測が可能となった。 それは商人の活動にとっては大きな意味をもっていた。 客観的な時間の計測が可能になったので、利子の計算が正確にできるようになり、 契約についても正確さが求められるようになった。 (支払いの日にちだけでなく、制限時間までつけられた?) それまでの旅の日程や距離は、宿泊日数とか馬を何頭とりかえたか、といった事実ではかっていた。 時計ができてから、ある町から別の町まで、歩いて何時間、馬で何時間という計算ができるようになった。 機械時計の発明は、人間関係が客観的な基準によって計られてゆくきっかけとなり、 均質的な時間や空間が生まれる出発点となった。 やがて、人間関係全体が合理的になった。 合理的というのは、わかりやすくいえば 予見できるようになるということである。 人間関係が偶然とか個性とか感情によって左右されるのは当然であるが、 社会の大きな枠組としての人間関係が予見しうるようになるということは、 その社会の行動力を非常に高めることになる。 ヨーロッパの契約社会の特性もますます強められていく。 整った反面、だんだんゆとりが無くなっていく社会。こうしてきゅうくつになっていったのだろう。
交響曲の源
ここは私はまだよくわからない。 わからないことが興味をそそるため、何度も読んで、音楽に詳しい人の話も聞いて まとめている。 さて、阿部先生は日本では疑問ももたずに西洋音楽を楽しんでいたのに、 ドイツに行ったらそのクラシック音楽が気になりだしたという。 日本では修道院生活も体験したから歌ミサも体験した。大学生の時は音楽喫茶に通って クラシック音楽を聴いていたのに。 ドイツに留学して1週間もたって慣れてきたとき、小さな町で 突然教会の鐘の音に襲われる。あちこちからも聞こえてくる鐘の音。 その鐘の交響曲に、日本の鐘の音とは違うものを感じ、中世の音の世界に関心がいき ついには西洋の交響曲に違和感を感じるようになった自分に気がつく。 どうも交響曲のもつ緊密に構成されたその構造が、阿部先生に違和感をもたらしたらしい。 確かに日本の伝統的音楽には構造性がない。他の人が言っていたが、邦楽は演奏する 奏者の力量で上手下手が明確に出る。ところが、ペートーベンの交響曲を例にとると ある程度ミスがなく演奏するなら、さまになって聞くことができる。その技量の差は あるだろうが、批評できるにはそれなりに訓練した者でないと差は見分けられないだろう。 学生時代には魅力に聞こえたクラシックの緻密な構造、それがドイツに来たら 違和感を感じるようになってしまった。 交響曲は多声音楽(ポリフォニー)を原型としている点が、邦楽と違う点である。 異なった音(声)が、異なったメロディーをかなでながら、全体としてひとつの ハーモニーをつくり出す。いわば世界全体を音で再構成しようとする姿勢が 交響曲にあるようだ。 そもそも中世の大学の四大科目とは、音楽、算数、幾何、天文であった。 音楽とは、世界を解釈するための思弁の一つの形と理解されていたのである。 音楽こそ世界を構成する原理だった、つまり世界は音にみちていて、 音楽とは音にみちた世界に調和を与えるものと考えられていたのである。 教会の立場では、異教の神々を拒否しキリスト教のみ残し、 世界の原理であるはずの音の世界を一元化することをめざし そのため単声音のグレゴリオ聖歌を普及させようとしたのであった。 それがだんだん発展してポリフォニーになっていた のではないかと阿部先生の本に書かれています。 (たいへん難しくて私にもわかりません) ここから先は音楽に得意な人から聞いた話ですが、バッハが 音楽の構造をまとめたそうです。ドイツ人は理論体系をまとめるのが得意ですから。 バッハの仕事から交響曲もできたし、ドイツの音楽が世界の財産になったのは、 そういう歴史があるそうです。 その人によると、バッハが生まれた頃死んでいる八橋検校の六段などは ポリフォニックな音楽ではないかと言っていました。 グレゴリオ聖歌の頃〜たぶん10世紀頃までは、 単旋律(みんなが同じ節を斉唱で歌う)の聖歌が歌われていた。 複数の旋律が独立して歌われるようになるきっかけは、 輪唱とかではないかと思われる。 輪唱は、同じ音程で、歌い始めるタイミングをずらす 訳だが、これを5度とか4度とか、音程もずらすと、 カノンになる訳である。そして更に、 カノンを駆使して主題の模倣旋律を巧みに重ね合わせて フーガとかに発展していったのではないだろうか。 バッハ辺りの緻密な対位法に至っては 鍵盤楽器の登場とは切り離して語れないだろう。 あるいは クォドリベットという世俗的な声楽曲において、 同じ旋律を歌っている複数の歌い手たちが、わざと(他の人とは) 旋律をくずして歌ったりする遊びもあったようで、 その辺から多声が生まれた可能性もあるかも知れない。 11世紀頃からの聖歌(ゴシック聖歌、ルネサンス聖歌)は、 多声音楽になっている(もっと前からかも)。 長調、短調ができるのは、1600年代頃からである。 長調、短調の機能和声を考慮して、ある規則のもとに、 複数旋律を重ね合わせる技法が、「対位法」(contrapunt)である。 いずれにせよ、西洋音楽や邦楽や琉球音楽やジャズやロックや その他もろもろの音楽が、そのような音楽形態に発展したのには、 環境や文化や偶然や様々な要素が複雑に関係していると思われる。 音階や調性に関しては、様々な地域で様々なものがあるが、 (まあそれでもピタゴラス律の中の、5音〜6音を取った音階、 つまり四七抜き系、ブルーススケール系で、似ているものが 多い)、敢えてそれらと比べて 西洋音楽が特異なのは、それを対位法や和声法として体系化した ことによって(より構造的で緻密な音楽が作曲可能な体系に) 発展したことではないかと思われる。 その意味で、バッハの音楽が、構造的で緻密なものを めざして成功した頂点だと思うのである(未だに不動の)。 その後の西洋音楽は、むしろ形式を破壊することに終始していて、 それはそれで、印象派のドビュッシーぐらいまでは、とても よく機能していたのではないかと思うが、 新ウイーン楽派の無調性音楽以降の現代音楽は、 新たな「機能」を模索して失敗し続けている一方、 ジャズとかはクラシック界の停滞を尻目に見ながら 着実に発展しているのではないだろうか。 (おたく的な解説ですが、ところどころ私にも理解できます) 阿部先生がクラシックに感じていた緻密な構成の息苦しさ それにやはり反発してジャズなどが発展してきたのではなかろうか。 新しい動きとはそういうものである。批判から生まれる新しい流れ。