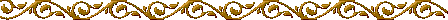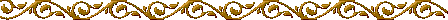
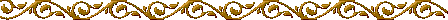
元一橋大学の学長の阿部謹也先生は、ドイツ中世の研究家として第一人者です。
阿部謹也先生の「中世の窓から」(朝日新聞社)は他の本には書かれていない知識が
そんなわけで阿部先生の講演を聞いた後で、私はこの本にサインをしていただきました。
多くて、ドイツ旅行をしたとき非常に思い当たることが多く、
この本の価値を改めて認めたものでした。
金貨を排泄する男
貨幣経済がかなり普及した13、4世紀に作られたゴシック建築の柱や壁に、
奇妙な姿の人間がお尻の穴から金貨を排泄している像が彫られているのがあります。
たとえば、北ドイツのゴスラーの市場に面したギルドハウス(現在はホテル)の壁に
このような像を見ることができます。これは貨幣を不潔なきたないものとみた、
当時の知識人の感情を伝えたものといえるでしょう。
何故貨幣は不潔と考えられたのでしょうか。11世紀以前のモノを媒介とする
人と人との関係は、人間の共同生活の非常に古い層に根差すものですから、
簡単にはなくなりません。贈与慣行は根強い倫理・掟として今日においてさえ
部分的には残っています。クリスマスや復活祭でもないのに、やたらに
物を受け取ることにやや抵抗があるヨーロッパの人でも、食事に招待すれば
喜んで応じてくれるでしょう。そして必ず返礼として招待してくれるでしょう。
それは対等の関係を保つための必須条件だからです。
お金を使わないで、行為や態度でお礼をいう良い時代があったということでしょう。
お金、お金の世の中で、お金を得るため犯罪さえも起きることがあります。
ところが、モノを与えた人(売り手)に対して、受け取った人(買手)が
すぐその場で何ら自分の人格とは関係がない金属片(貨幣)を渡して、
何の返礼もせず去ってしまったらどうでしょうか。11世紀以前の倫理の世界
に生きていた人ならば、腹をたてるよりは相手を軽蔑したでしょう。
モノの交換の背後には、本来人格と人格のふれあいがあったからです。
あるドイツ留学した研究者が書いていたが、そのときは船でドイツまで行った。
途中、エジプトで降りて見物などしたが、盗難にあってしまった。
困り果てていたとき現地の人から温かいもてなしを受けたので、
別れるときなけなしのお金を少しばかり渡そうとした。
とたんに彼らは怒りだしたという。自分たちの真心がお金という代価でとりあつかわ
れたことが彼らの倫理観にさわったらしい。
その経験でまずカルチャーショックを受けたと書いてあった。
現代でも、その土地によっては、その人間関係を大切にするためのつきあいのルール
とか気配りがあるのだろう。
9世紀の段階では、貨幣は貴金属としての価値をもっており、王侯・貴族も
祈祷書を貨幣で飾ったりしていました。しかし11世紀には、貨幣は人びとが
追い求めるものであると同時に他方で不潔なものとしてのイメージが生まれて
ゆきます。そこには、新しい貨幣を媒介にした経済秩序が確立されてゆく反面で、
その秩序に適した新しい倫理を生み出すことができずにいる人びとのいらだちが
表現されていたのです。
日本でも明治の時に、金色夜叉のお宮のように、お金で心をうつす女性に
今でも金の力でなんでも買いあさり横柄な態度をとるアメリカ人旅行者は
しかし、人間を幸せにするのもお金なのです。
お金は心と心のやりとりとは別の力をもちますから。
私も留学生研修旅行をして、鉱山の町ゴスラーの町の広場の建物の壁に
怒りをおぼえる人もいた。
ヨーロッパの嫌われ者。
もちろん団体旅行で食事の作法もエチケットも守らない日本人旅行団も
彼らには内心軽蔑されています。
ちょっと美味しい食べ物を食べたり、新しい上着を買ったら、元気になる。
中世でもそういったお金の力に人々が気がついて、それでも人間関係を
ドライなものにして、うるおいとか、やさしさをどこかに置いていく、
透明な人間関係を作るお金に対して、不信感とか恐怖を感じていた
人々は多かったのでしょう。
お金によって、心と心がより強く結びつくこともありますが、
その反対に心と心を切り離すこともあんがいあるのではないでしょうか。
飾ってあった「金貨を排泄する男」の像を見てきました。
石の聖体安置塔
ニュルンベルクのロレンツ教会に入ると、正面左手に高さ20メートルもある
聖体安置塔があるのに気がつきます。
かがんだ3人の男が塔の台を背中で支えているように見えます。
前にはつちとたがねをもった中年の男、祭壇よりには、たがねを手にした男、
反対側には手におのをもった老人が見えます。
これこそニュルンベルクの石の芸術家アダム・クラフトの作品で、
この3人がアダム・クラフトと徒弟、職人なのです。
この作品は1493〜96年につくられ、クラフトは1455〜60年頃
に生まれていますから、この頃のクラフトの年齢を推定できるのです。
かつて美術史家ヴェルフリンはこの聖体安置塔を後期ゴシックの精華と
たたえましたが、これこそニュルンベルクの石工の頂点に立つ作品ということが
できるでしょう。
聖体安置塔をはじめて見た人は、傍らによってしさいに眺めるまでは、
それが石で作られていることが信じられないでしょう。
実は私も最初に見たときは、これがそんなにたいしたものとは気がつかなかった。
同行のイギリス人がガイドブックを片手に、しきりにこの聖体安置塔を眺めて
いたのだが、そのときは彼の態度を理解できなかったのだった。
後からこの本を読み直して、それではと再び見に行ったものである。
確かにこれが石でできているとは、信じられない。それくらい精巧なものです。
この聖体安置塔が制作されるとき、契約書の中でクラフトは石造の聖体安置塔を
芸術的であり、しかも精巧につくることを約束しています。
現代の芸術作品なら必ずしも精巧である必要はないでしょう。現代の芸術的という
言葉には、日常の用に供しうるという意味を越えたものがありますから、芸術作品
は日常の用とは無縁なものとしても成立しうるのです。ところがクラフトは
聖体安置塔を芸術作品であると同時に、実際の役に立つ精巧なものとして作る
ことを約束しているのです。
ここに中世の職人の面目があるといえるでしょう。彼らにとってすべての
作品は、芸術的であると同時に実用的でなければならなかったのです。
契約書ではさらに人の目にふれやすい部分は特に入念につくらなければならない
とされ、親方クラフトが、3、4人の職人と共に自ら手を下すことという
条件もつけられていました。
クラフトの聖体安置塔はまるでゴシック大聖堂のミニチュアであるかに見えます。
クラフトは実際にこの聖体安置塔を装飾品としてでなく、青空にそびえたつ現実の
大聖堂としてつくったのに違いないのです。
オイレンシュピーゲル
民衆本『ティル・オイレンシュピーゲル』の84話に次のような話があります。
オイレンシュピーゲルはある旅籠にきて、おかみさんにオイレンシュピーゲルを
知っているかとたずねます。
おかみさんは会ったことはことはないけれども、とんでもないやくざ者だと
聞いていると答えます。
オイレンシュピーゲルは「本人に会ってもいないのにどうしてやくざ者だという
のかね」と聞くと、世間が皆そういうのだからという答えます。
つまり、おかみさんは客から聞いた話をそのまま他人に話しているのです。
あくる朝、オイレンシュピーゲルはおかみさんをつかまえて、お尻を暖炉の火に
降ろして、やけどをさせてしまいます。そして、オイレンシュピーゲルは言ったのです。
「これからはオイレンシュピーゲルがやくざ者だといってもいいぜ。
お前さんは自分の肌でそのことを知ったのだから」
この話を読んでも、この話の背景にある意味を我々現代人はよくわかりません。
この話は、人から聞いた話をうのみにしてはいけないとか、
自分の目で確かめるまで噂を信じてはいけない、といった教訓話だけではないのです。
この話が書かれた15、6世紀の中世の時代は、風評に基づく裁判が放浪者や
よそ者に対して適用されつつあった時代でした。旅籠のおかみさんは何の悪意もなく、
ただ噂話を噂話としてしゃべっただけでも、放浪者の側からみると、自分の生命に
かかわることになるのです。
「噂ではやくざ者です」と証言をする者が7人いれば、事実はどうであれ、
断罪できたのです。おそろしいことです。
『オイレンシュピーゲル』の著者は民衆本のいたるところで、このような新しい都市
法に対して厳しい批判をしているのです。おそらく著者は、こうした事態が放浪者
だけでなく、一般の市民にも及んでくることを、十分に予測していたからでしょう。
中世のこっけい本オイレンシュピーゲルは、基礎ドイツ語ででもよく紹介されていた。
この話は噂話の怖さを語っています。現代でも、どこかで誰かが他の人たちから
新しい時代についていけない人、新しい時代の法律や人の考え方について
オイレンシュピーゲルの作者は、きっと考えることがいっぱいあったのでしょう。
あることないこと噂をたてられ困っている人はいるでしょう。
だから裁判では証拠をちゃんと確認しながらすすめられるわけです。
ホップという名の犬
オイレンシュピーゲルがアインベックで麦酒製造職人となり、親方にホップを入れろと言われ
ホップという名の犬をホップの代わりに煮込んだこと(第47話)
オイレンシュピーゲルはリューベック南方のメルンで、1350年にペストのため病死した。
メルンでは16世紀になっても「ヤチヤナギ入りビール」が造られていた。
アインベックで、ホップという名の犬を入れたビール造りで、とんだ茶番を演じてしまったオイレンシュピーゲルにとって、
「ヤチヤナギ入りビール」にこだわり続けていたメルンという町が終焉の地になろうとは、なんと皮肉なことであろう。
高橋壯:ホップとビールの出合いを探る
宗教裁判にのぞむルターを元気づけた一杯のアインベック・ビール
靴職人と古靴修理職人
靴は∃ーロッパの人びとにとって生きてゆくうえに欠くことのできない生活必需品
でしたが、自分の足に合わせて作らせると非常に高価で貧乏入には容易に手が出せ
なかったのです。貧しい職人や農民は古靴修理職人から古靴を買ってはいていた
のです。こうして王侯貴族や豊かな市民のための靴を作る靴職人と、貧しい職人や
農民の靴をつくろう古靴修理職人とがはっきり職種としても分かれることとなり、
後者の組合は社会的序列においても劣るものとみられていたのです。
伝説によると1470年頃にポンメルン出身のハンス・ロデガストという靴職人が
ハンブルクヘやってきました。ちょうどハンブルクの靴職人が市参事会と衝突して
大勢の職人が遍歴に出てしまったあとで靴職人が不足していたので、ある親方が
ハンスの経歴や出生も問わずに職人として採用してくれたのです。
実はハンスはヴェンド人でした。ヴェンド人とは紀元後600年頃にドニエストル
地方から進出してきた西スラヴ人で、エルベ川流域に居住し、今日でもラウジッツ
の北部に住んでいます。中世においてすでに少数民族としてドイツ人から蔑視され
ていました。ヴェンド人は、ジプシーや賎民と同じく、手工業職人になれなかった
のです。ポンメルンではあまり問題はなかったのですが、リューベックを経て
ハンブルクヘ来たとき、キリスト教徒たちが、ヴェンド人のことをあまりに悪し
ざまにいい、馬鹿にしているのに、ハンスは驚いてしまったのです。
都市の中でヴェンド人が暮らしてゆこうとすれば全く孤立して生きるほかありません
でした。しかしハンスにはやがて結婚したいと思う娘ができました。結婚するため
にはまず親方にならなければなりません。親方になるためには市民権をとらねば
なりませんが、ハンスはそのための金はもう貯めていました。古靴修理職人には
容易になれたでしょうが、それでは娘と結婚することはできないと思われたのです。
それほど古靴修理職人の地位は低かったのです。しかしヴェンド人であることは
隠しようもありませんでした。
思いあまったハンスは市参事会に行って市民権をとろうとしたのですが、出生証明
を求められ、それがないためにヴェンド人ではないかと疑われてにべもなく拒絶
されてしまいました。市の法律にはっきりとヴェンド人を職人に採用しては
ならないとあったからです。そこでハンスは自分はヴェンド人ではないと主張し、
しかもハンブルクではどんな靴職人も足もとに及ばない技術をもっていて、
市参事会員が求める靴ならなんでもつくってみせると豪語したのです。
市参事会員たちはハンスをからかって「明日の朝、日が昇る前に縫い目のない靴を
ー足つくってきたら市民権をやろう。ただし、ヴェンド人であることがばれたら
市民権も取り消されるぞ」といったのです。事実1466年にはハンス・シュヴィーネゲル
という男が偽って市民権をとり、あとでばれて台帳から消されたことがありました。
ハンスは家に戻ると仕事机の前で頭をかかえこんでしまいました。どう考えても
あすの朝までに縫い目のない靴を作ることなどできるはずがないからです。
思いあまったハンスはついに悪魔を呼んだのです。悪魔はすぐにやってきました。
そこでハンスは自分の不死の魂を悪魔にやることを約束し、さらに主の名前を二度と
ロにしないこと、もしロにしたらその瞬間に悪魔のものとなることも約束したのです。
すると悪魔はまたたく間に縫い日のない長靴をつくりあげると飛んで帰ってゆき
ました。翌朝その長靴をもって市参事会を訪れたハンスは市民権を請求しました。
市参事会員はこれをみて仰天しましたが、ひとたび約束したことですからハンスに
市民権を与えることにし、ハンスは市民としての宣誓をすることになりました。
ハンスが「主なる神が私を助け、聖なる言葉を……」といい終わらないうちに突如
として稲妻がはしり、雷鳴がとどろいて、ハンス・ロデガストは床に打ちたおされ、
そのまま立ち上がりませんでした。
市参事会員も気を失ったのですが、目を覚ましてみると明らかにヴェンド人と
わかるハンスの死体がそこにあつたのです。悪魔のつくったこの長靴は大聖堂に
長い間つるされ、組合の規則を破ることのないように人びとに注意を喚起していた
のですが、19世紀初頭に大聖堂がこわされた時、この長靴も砲兵隊の武器庫へ
移されたのです。ある作家がこの長靴を調べたところ縫い日のない靴ではなかった
そうですが、それは後日談です。
ヴェンド人であったハンスも古靴修理職人にはなりたくなかったのです。古靴修理
職人の多くは小さな仕事場しかもたず、天気が良いときには青空市場に道具をもち
出して修理をしていました。貧しい古靴修理職人は道具を肩にしょって村から
村へ渡り歩き、鍋釜の修理をしたジプシーのように注文をとっていたのです。
古靴修理職人は多くの都市で市民権をとれませんでしたから、何らの政治的特権も
もっていませんでした。フランクフルト・アム・マインでは靴職人の親方は市参事会
に代表を送ることができましたが、古靴修理職人には同じ権利が与えられなかった
のです。古靴修理職人は市の営業許可をとらなければならなかったのですが、
1740年にはフランクフルト市参事会は今後は古靴修理職人は登録させないと
きめました。しかし靴職人が古靴の修理をしようとしなかったので、この規定を
撤回しなければなりませんでした。18世紀においてなお古靴修理職人から靴を
買わなければならない多くの貧民がいたからです。
靴職人とマイナーな古靴修理職人という二層階級があったなんて、中世の階級社会
彼はヴェンド人だった。つまりスラブ系の人間だったので、なかなかドイツ人社会
ヴェンド人の町の人々はなかなかドイツ人に受け入れてもらえないし、時々襲われる
その家の作りを専門家が調べて朝日ジャーナルに載せていました。
朝日ジャーナルにこの文章を書いていたのは、当時ダルムシュタットに住んでいた
ここにも悪魔伝説が残っていた。無理なことを要求された職人はやはり悪魔の助け
を考えてしまいますね。市参事会に代表を送られたら、自分たちの意見も反映され
するし、立場も保護されることができる。だから、古靴修理職人もいつか靴職人に
なりたいと願っていたことでしょう。
に受け入れられなかったのでしょう。ヴェンド人も少しずつドイツ社会の中に入り
込んで同化していったのでしょう。日本の中華街や在日の人の苦労を連想します。
ことがあったから、その町の作りは一風変わっていたようです。外敵に対して町を
取り囲んで守るよう家の配置がされていたと記憶しています。
そこには、同じように守りの家のスタイル(丸くなって360度にわたって壁が
ぐるりと取り囲み小さな窓だけあいている)の中国の客家(はっか)住居も紹介
されてありました。客家の家は内側はオープンになっていて、まあ野球場や
コロシアムを連想する構造になっています。条件が似ていると、どうしても同じ
ような家の作り方になるらしい。きっと両者は情報交換をしたわけでしないでしょう。
春日井博士。私は面識があるので後日その朝日ジャーナルのことを手紙に書いたら、
よく読んでいると誉められましたが。
を求めることになっている。