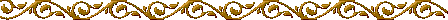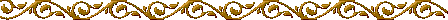
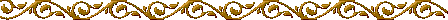
ユダヤ人
ユダヤ人は中世において厳しい迫害を受けていたと一般に考えられていますが、 それほど単純なものではありません。 ニュルンベルクでもフランクフルトでも市民権をもっていたユダヤ人もいましたし、 市参事会員と同格のユダヤ人もいたのです。 たしかにユダヤ人迫害は11世紀末からはじまっていますが、 ユダヤ人全体がいわゆるゲットーにおしこめられ、苦難の道を歩むようになるのは むしろ近世に入ってからなのです。中世におけるユダヤ人の社会生活は、16世紀 から18世紀までのユダヤ人の地位と比べれば、比較にならないほど良好で あったということができるでしょう。 ユダヤ人の職業にしても必ずしも金融業だけでなくワイン取引を大規模に営んで いましたし、都市内では仕立屋、パン屋、鍛冶屋、製本屋、彫刻家、カルタ作り、 運送業なども営んでいました。のちになるとこれらの手工業は主として ユダヤ人相手の職業となりますが、医者などはキリスト教徒からも信頼され、 ユダヤ人女性も医者として活躍していました。 ところが11世紀頃からユダヤ人の職業はもっばら商業、とりわけ金貸し業に しぼられてゆきました。 イタリア、フランス、ドイツ、イベリア半島のどこでも同じような現象がみられたのです。 キリスト教徒とは異なった宗教を信じ、金融業に専業化してゆくユダヤ人の定住地が 各都市に生まれていきました。 そしてそれとほぼ同じ頃にどこでもユダヤ人迫害がはじまるのです。 1009年から10年にかけて、オルレアンとリモージュのユダヤ人は立ち去るか、 キリスト教に改宗するか、それとも死ぬか、三つにひとつを選ぶよう命ぜられた といいます。 1096年5月にシュパイエル郊外で十字軍兵士がユダヤ人のシナゴーグを襲い、 ヴォルムスのユダヤ人居住区でも同じような事件がありました。 受洗を拒否するユダヤ成人はみな殺され、幼児すら殺されるか洗礼を強要されたのです。 これらのユダヤ人襲撃の主力となったのは、騎士たちによって編成された十字軍兵士 というよりは、一般民衆の十字軍参加者たちだったのです。この頃の年代記作者に よりますと、洗礼を拒否するユダヤ人を殺せば自分の罪がゆるされると信じていた 人びとが多かったといわれます。遠くエルサレムまで十字軍遠征に旅立とうと したところ、日の前に敵であるユダヤ人がいたのでまずかれらを片付けたのだ という者もいました。 11世紀まで宗教を異にしながらもさしたるあつれきもなく、 不安定ながら商人としてキリスト教徒と平和的に共存しえたユダヤ人の地位が、 この頃に急激に変化し、ユダヤ人はこのあと近代にいたるまで苦難の道を歩む ことになります。そこにはいったいどんな事情があったのでしょうか。 12世紀頃からユダヤ人が正餐のパン「聖体」をけがしているとか、 泉に毒を流しているという噂も伝わり、いずれのばあいにもユダヤ人虐殺の口実 となっているのです。 聖餐のパンがユダヤ人によってけがされているという噂について、リトルは 次のように説明しています。 まず第一に聖餐のパンとぶどう洒がキリストの肉と血に変化するという化体説は、 1215年のラテラン公会議でようやく正式に認められたものですが、 この考え方には長い問疑問が絶えず、納得しない人びとの数は少なくなかった といわれます。 キリスト教徒はユダヤ人が爪を聖体につきたて、聖体が血を流しているイメージを つくりあげることによって、化体説に対する自分自身の意識下の疑いを ユダヤ人に投影させたのだというのです。 リトルはキリスト教徒によるユダヤ人迫害はキリスト教徒自身の貨幣に対する 意識の反映だとみています。ユダヤ大衡が襲撃されたとき、しばしば帳簿類が 奪われたり、焼かれたりしています。キリスト教徒の借用証文が焼かれたのですが、 そこに単に損得の問題だけをみるのでは不十分です。 「キリスト教徒はユダヤ人が利益を得るために金勘定をしている姿を憎んだのですが、 キリスト教徒自身正しいことではないことを知りながら、それと同じことを 行なっていたのです。自分自身がこのような罪にまきこまれていたために、 それをユダヤ人に投影したのです。いわばキリスト教徒が〔貨幣を媒介とする〕 営利経済のなかに、うまく適応できなかったことの身代わりとされたのが ユダヤ人であったのです。」 (リトル) 12世紀のクリューニー修道院長、尊者ペトルスは教会から儀式用の聖杯が盗まれ、 ユダヤ人の店に質入れされた事件について王に訴えています。盗みそれ自体が 問題にされているのではなく、ユダヤ人の質屋が聖杯に冒涜行為をしたのではないか、 と訴えているのです。 リトルはこの事件をまさにこの時代のキリスト教徒とユダヤ人の関係を知るうえで 恰好の事例としています。何故ならペトルスの議論は教会から聖餐用の聖杯が 盗まれたという事実から人びとの注意をそらしているからです。 聖杯は現実に貨幣にかえられているのです。おそらくキリスト教徒が聖杯を盗んで ユダヤ人の質屋で貨幣にかえているのですが、このことを隠して、ユダヤ人の質屋が 質物に対して冒涜行為を働いたとして非難しているわけです。 実際にペトルスの時代に、クリユーニー修道院はユダヤ人の金貸しから年収の5倍もの 金を借り、大きな負債を負っていました。ある後援者が1149年に修道院の借金を 肩代わりして支払ったところ、かつて自分が修道院に寄進した十字架の金の飾りが はずされて売り払われていました。 同じくリトルによると、ペトルスは、ルイ七世が十字軍に出発しようとしていた ときに、サラセン人よりも悪い連中がすぐ傍にいるのに、何のために遠い国まで 十字軍に行くのかと述べたそうです。 ペトルス自身はユダヤ人を殺せとすすめたわけではありませんが、 ユダヤ人に遠征の埋め合わせをさせるべきだと考えていたようです。 ユダヤ人は額に汗して働きもせずに蔵に食物やワインをいっぱいにし、財布も ふくれあがっている。 彼らはキリスト教徒からそれらを盗んだのだといっているからです。 同じく12世紀のクレールボーの修道院長ベルナールも、金貸し業はすべて ユダヤ人の仕事とみなしていました。「ユダヤ人がいないとキリスト教徒の金貸し がユダヤ人になります。これはユダヤ人よりも悪い代物です。 彼らは必要ならキリスト教徒と呼ばれますが、洗礼を受けたユダヤ人ですらないのです。」 このようにベルナールがいうとき、彼はキリスト教徒も貨幣経済の流れのなかで金貸し にならざるをえなくなっていることを知ってはいたのですが、認めることは できなかったのでしょう。 実際、ユダヤ人だけでなく、キリスト教徒も数多く金融業に従事していたのですが、 余貸しはもっぱらユダヤ人の仕事として非難されることになりました。 キリスト教徒の倫理のなかでは金貸し行為は容認されないことでしたが、 11世紀以後の貨幣経済の全面的展開のなかで、町に住むキリスト教徒は 多かれ少なかれそれにまきこまれていたのです。自ら正当化しえない行為を 行なっていたキリスト教徒は、その罪の意識をユダヤ人に転嫁し、 ユダヤ人を攻撃したのですが、それはおのれを攻撃することでもあったのです。 しかし罪の意識はやがて敵意に転化します。敵意が暴力と結びついたとき迫害が 起こるのです。 リトルはおおよそ以上のようにユダヤ人迫害の原因を分析していますが、 このような分析は1878年のロッシャーの研究をより深めたものとみることが できます。 ロッシヤーは農耕社会のヨーロッパでは、よそ者のユダヤ人などに商業が 委ねられていたのに対し、キリスト教徒自ら商業に従事するようになると、 ユダヤ人が不必要になり、このような商業における対立、競争のなかから 反ユダヤ人感情が芽生えてきたと説明しているのです。 ロッシャーの考え方は基本的な点で正しいでしょうが、たんなるねたみだけでなく、 キリスト教徒がモノを媒介とする関係から敏速に新しい貨幣経済の倫理になしむ ことができなかった点に、反感が生ずる原因があったとみられるのです。それ以前の人と人との関係はモノを媒介にして結ばれ、目に見えないが しっかりしたルールがあったのに、11世紀以後急速に発展してきた貨幣経済に、 多くの人々がうまく適応できなかったのだろう。 モノをやりとりして人間関係を作っていたとき、そういう慣習にとらわれない ユダヤ人の出現は人々にとまどいを与えたにちがいない。 ユダヤ人は古くから商業の才にたけているとみられていました。 それは三大陸に分かれて住んでいたユダヤ人が、商取引においても「タルムード」 という独自の法によって律せられていたためなのですが、11世紀における 貨幣経済の展開は彼らには恰好の舞台でした。 多くの人びとが新しい貨幣経済の展開のなかで古い倫理にとらわれてうまく適応 できないでいる間に、ユダヤ人はさっそうとして巨富を蓄えてゆきました。 ユダヤ人の時代が到来したのです。かつては異国の商業民として対等に扱われ なかったのに、今ではキリスト教徒が商業民の仲間入りをしたのです。 そしてこの点ではユダヤ人ははるかに先輩でした。 ユダヤ人は巨富を利用して町のなかに立派なシナゴーグを建ててゆきました。 こうした事態はキリスト教徒にとっては大きな脅威でした。成り上がり者のユダヤ人 に対してはまず貧民が反発したのです。自分たちより下の存在だと思っていた ユダヤ人がまたたく間に巨富を蓄え、立派な家を構えるようになったからです。
こうして民衆はユダヤ人を憎んで襲撃したのだ。 トマス・アクイナスがいうように、金を貸して利子をとることは存在しないものを 売ることだから正義に反し許されない、というのが教会の正式な見解でした。 しかしながら都市の建設それ自体、莫大な資金を要することはいうまでもありません。 商業が利益をあげるほとんど唯一の手段であった中世社会において、経験豊かな 商人として巨富を貯えていたユダヤ人がそこで登場するのは当然のことです。 ニュルンベルクでもコンラート三世の時代に町を拡大し、その資金を調達するために ユダヤ人を誘致したのです。 一方でユダヤ人の資金をあてにしながらも、他方でユダヤ人の活動を大幅に制限 しようとした結果、中世末期の矛盾する対ユダヤ人政策がとられたのです。 1451年のバンベルクの会議で枢機卿ニコラウス・クサーヌスは、 ユダヤ人がキリスト教徒に対して高利で金を貸すことを禁したのですが、 それに対しては皇帝も市当局も必ずしもすぐに賀意を示しませんでした。 ユダヤ人は皇帝にとつてもニュルンベルク商人にとってもまだ必要だったからです。 G・ミッヒェルフェルグーの研究によると、利子をとることを禁じられていた キリスト教徒の商人は、債務者の支払いが遅れたばあいでも延滞利子をとることが できません。そこでその間ユダヤ人から債権分の金を借り、債務者がユダヤ人に 利子をつけて返済するようにしていたのです。こうした裏取引によって キリスト教徒の商人は利子はとっていないという建前をとることができたのです。 ところが1479年の都市法においてユダヤ人の金融業が禁じられたのです。 数百年にわたってニュルンベルクにおける金融業を独占していたユダヤ人の地位に 大きな変化が生したのです。市当局は市の両替銀行の設立を定め、 皇帝マクシミリアン1世からその許可を求め、同時にユダヤ人の追放についても 同意を求めました。 この政策の大きな転換は、いうまでもなく、かつてユダヤ人が占めていた地位に キリスト教徒がとって代わったことを示しているのです。どのように活発な商業活動を 行おうとも、ニュルンベルク商人の活動が中世都市としてのニュルンベルクの社会倫理 のわく内にある限り、その発展には限度がありました。メンデル家の三兄弟のように、 努力して蓄積した富を養老院や病院の建設に使うとき、彼岸における救済と同時に、 このような贈与によって人びとの尊敬を集め、社会的地位の向上も求められて いたのです。キリスト教徒がこのような目にみえない絆としての社会倫理に 拘束されていた限りで、ユダヤ人にも活躍の場が約束されていたのです。 教会が利子を禁止していたのも、かつてのモノを媒介とする人間の関係を転換 させようとしていたからでした。 教会は「何ものをも期待することなく互いに与えよ」と教えていたのです。 教会自身も守ることができなかったこのような教えが、貨幣経済の展開のなかで 完全に空文と化したとき、カルヴァンの「貨幣は子を生む」という教えが生まれ、 ユダヤ人は必要でなくなるのです。このとき市民の間に新しい人間の関係が 生まれることになります。
「貨幣は子を生む」という資本主義的思想を受け入れたのはキリスト教の革命だったろう。